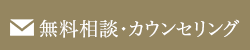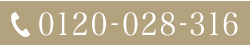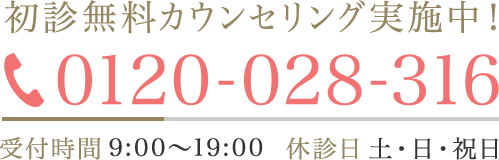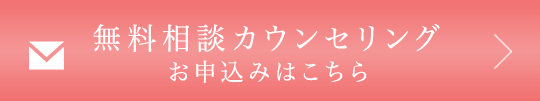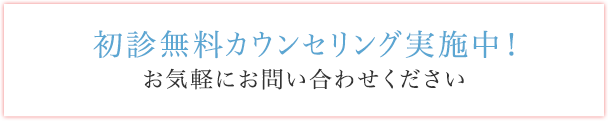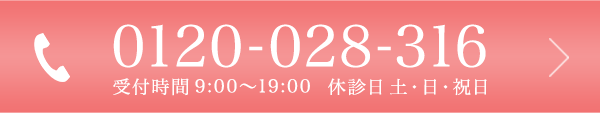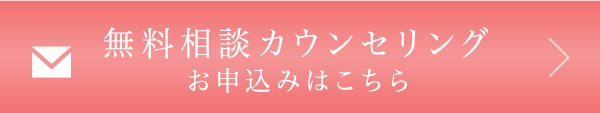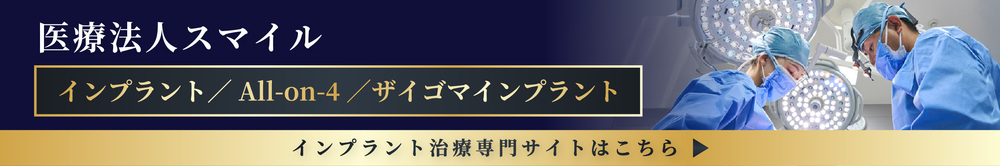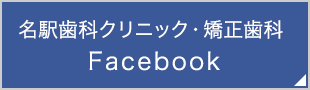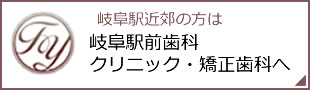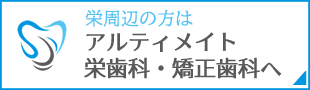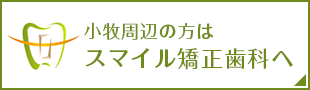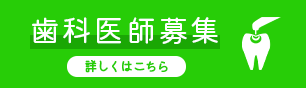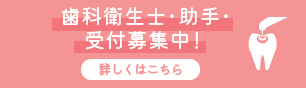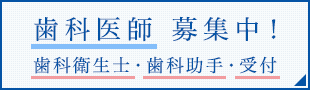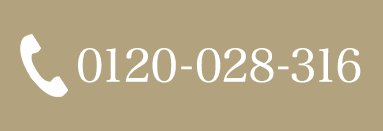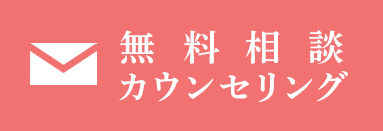整っている噛み合わせを目指そう

①日頃の癖を減らそう
舌の位置が悪かったり、爪を噛む、頬づえをつくなどの悪習慣があれば、それが歯並びの悪化に直結します。日常の悪い習慣は、少しずつ改善できるように意識しましょう。その積み重ねが、整っている歯並びに繋がります。
②咀嚼する時に意識しよう
食べ物を噛むときや、重い荷物を持つときは、左右のバランスを整えるようにしましょう。歯を片方ばかりで噛み続けたり、片方ばかりで荷物を持ったりすると、それが身体のバランスの歪みに関係します。偏った負担がアゴの骨、関節に悪影響を与えるので、左と右の差に気をつけて生活を送りましょう。
③肩の位置を気にしよう
直立した時に、左右の肩の高さが床と平行になっているか確認しましょう。片方に傾いている場合は、噛み合わせに悪い影響が出ている可能性があります。
④肩甲骨や骨盤は歪んでいませんか
肩甲骨が片方にズレていたり、骨盤が片方に偏っていたりしないかを確認してみましょう。自分で確認することは困難ですので、誰かにチェックもらいましょう。
直立した時に身体を後ろから確認してもらったときに、左と右どちらかに偏っているなどの症状があれば、噛み合わせにも悪影響が出るかもしれません。
⑤口元の筋肉をほぐそう
筋肉が日頃から緊張している箇所は、ストレッチやマッサージでほぐしましょう。筋肉のバランスが偏らない様に気をつけながら、耳の下などのアゴ周辺、そしてそこから繋がっている肩や上背を柔らかくします。
⑥噛み合わせの矯正を検討しよう
噛み合わせの悪影響を身体全体に広めないためには、噛み合わせを正しくすることが重要です。歯並びは自分一人で改善できるものではありませんので、現状噛み合わせや歯並びが悪化している場合は、歯科医院による歯列矯正などで噛み合わせを整えていきましょう。
噛み合わせが悪化する要因を知ろう
①日頃の食事を整えよう
柔らかい料理ばかり食べていると、アゴの骨格が徐々に弱くなってしまい、噛み合わせが悪化してしまいます。以前はお煎餅や豆、魚の骨など、噛む際に力が必要な食べ物を沢山食べていた日本の食文化でしたが、食事の内容が欧米に近づき、柔らかい食べ物が大変増えました。
幼い頃からの食生活であまりに固くないものばかり食事していると、口元の骨格や筋肉に刺激が入らずに、噛み合わせが悪化します。
②日頃の姿勢が悪い場合
姿勢が良くないままで生活を送ると、それが身体の歪みに直結します。アゴの骨格や筋肉にも悪影響を及ぼして、噛み合わせが不正になることが予想されます。
③同じ動座を繰り返しているとき
同じルーティンの機械的な作業をする場合など、繰り返し同様の動きを続けていると身体のバランスが悪くなります。左と右のどちらかの身体の1箇所のみを使い続けたり、筋肉に負担が加わったりすれば、それが要因で噛み合わせに悪影響を与える場合があります。
④歯がない状態が続いている
歯が何かしらの要因で抜けてしまったのを放置していると、歯並びが悪化したり、上下のアゴの噛み合わせのバランスが悪くなります。
上と下の歯がしっかりと噛みあうことで噛み合わせは保たれますが、下の歯が抜けた場合には、上の歯に対応する歯を失うことになり、周囲の歯への力の加わり方が変わってしまいます。
自分では大きな問題だと感じていなくても、後から大きな影響が発生することがあるので気をつけましょう。
⑤先天的による要因
例えば、遺伝によって噛み合わせが悪化しやすい方がいらっしゃいます。アゴの関節の状態や歯並びが不正の場合、その状況には個人差もございます。そして、アゴが突出しているなどの特徴が遺伝するケースもあり、生まれながらに噛み合わせが悪化しやすい傾向の方も沢山いらっしゃいます。
⑥虫歯による噛み合わせの悪化
虫歯菌は酸を発生させ歯を溶解させます。虫歯があるのをそのままに放置していると、歯が酸によって溶解してしまい、歯の原型が維持できないことにつながります。歯の形が変わってしまえば、それが噛み合わせにも悪影響を与えると言えます。
⑦歯周病が要因の場合
歯周病が発症すると、歯の根元が安定しなくなりぐらついてしまいます。それが要因で、噛み合わせや歯並びが変形することがあります。歯の根元が下がるのは、歯周病の症状の他に、老化現象のひとつと言えます。