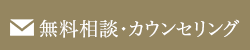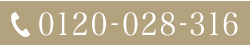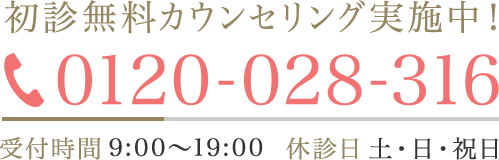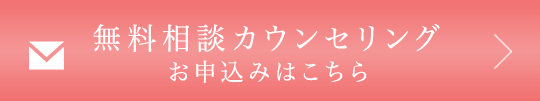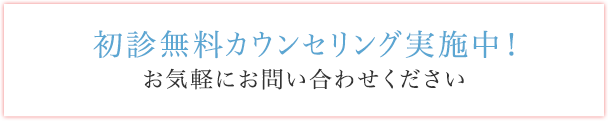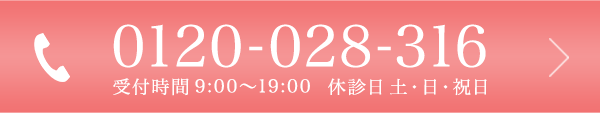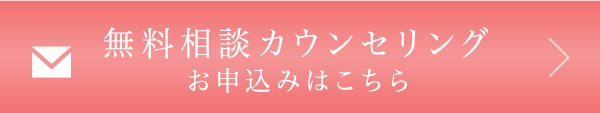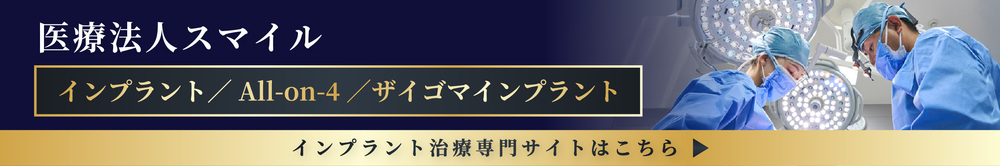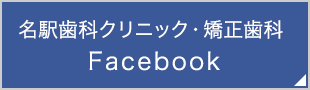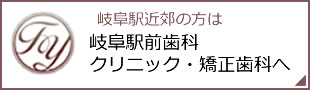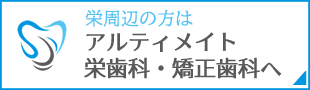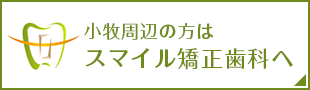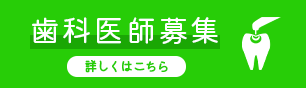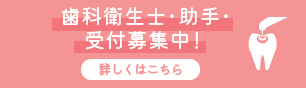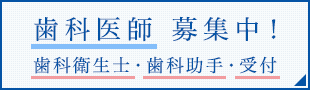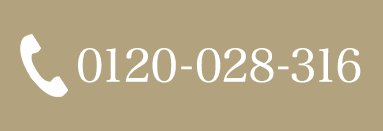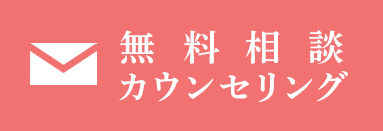インプラント治療を行う場合、寿命はどれくらいなのか、気になる方もいるでしょう。
そもそもインプラントは埋入するインプラント体と上部構造に分かれており、使用する環境や状況によって寿命が変わるため、厳密に寿命を割り出すことはできません。
一方、平均どれくらい寿命があるのかについてはある程度予想可能です。
この記事では、インプラントの寿命はどれくらいか、寿命が来たらどうするか、寿命が縮む原因、寿命を延ばす方法、寿命の判断基準、再手術が必要となるケースについてご紹介します。
インプラントの寿命はどれくらい?

インプラントの寿命は、平均10〜15年とされるのが一般的です。
ここでは、インプラントの平均寿命はどれくらいかについて詳しく解説します。
インプラントの平均寿命:10~15年
一般的に、インプラントの平均寿命は10〜15年とされています。
適切なメンテナンスを行った場合は、20年以上機能するケースも珍しくありません。
実際、日本口腔インプラント学会によれば、10年経過時のインプラント残存率は90%以上と報告されています。
一方、インプラント体(顎骨に埋入されるチタン製のネジ部分)は半永久的に機能する可能性がありますが、上部構造は数年〜数十年で交換が必要となる場合があるため、注意が必要です。
使用者によって寿命が左右されるため、適切な使用方法を知っておくことが重要です。
入れ歯やブリッジとの比較
インプラントの耐用年数は、入れ歯やブリッジと比較して優れています。
入れ歯は平均5年前後、ブリッジは7〜10年前後が目安とされており、同様の用途で使用するものと比べるとインプラントは比較的寿命が長持ちしやすいです。
周りの健康な歯にも負担をかけにくいインプラントは、口内全体の歯を守るという意味でも優秀といえるでしょう。
インプラントの寿命が来たらどうする?

インプラントの寿命が尽きた場合、適切な処置が必要です。
ここでは、インプラントの寿命が来たらどうするかについて詳しく解説します。
原因に合わせて治療を受ける
インプラントの寿命が尽きた場合、原因に合わせて治療を受ける必要があります。
例えば、インプラント体の動揺や骨吸収が認められる場合には除去後の再手術、破損が認められる場合は上部構造の再製作といった具合です。
まずは、歯科用CTや歯周ポケット検査で正確に診断し、原因に応じた対応を行うことが求められるでしょう。
保証期間と条件を確認する
歯科医院では、インプラントに対して一定の保証期間を設けていることがあるため、保証期間と条件を確認することも忘れないようにしましょう。
一般的に、インプラント体に対しては10年保証、上部構造に対しては5年保証という具合に設けられているため、担当医に確認しておくと安心です。
しかし、保障の適用には定期的にメンテナンスを受けているなどいくつかの条件があるため、治療を受けたクリニックの保証内容も確認しておく必要があります。
インプラントの寿命が縮む原因

インプラントは、使用者によって寿命が縮むことも珍しくないため、どのような原因があるのかについては知っておきたいところです。
ここでは、インプラントの寿命が縮む原因について詳しく解説します。
細菌による感染症
細菌による感染症を発症すると、インプラントの寿命が縮むことがあります。
例えば、歯周病と同様の細菌感染によって引き起こされるインプラント周囲炎といった炎症を放置すると、インプラント体を支える骨が吸収されて脱落しやすくなります。
一度脱落すると、再度手術が必要となり、処置が大変です。
ゆえに、脱落を防ぐために口腔衛生の維持と早期発見による対処が重要となるでしょう。
インプラント周囲炎の他にも、歯周病の進行によって上部構造が影響を受ける場合もあるため、毎日の歯磨きを徹底することが重要です。
担当医のスキル不足
担当医のスキル不足によって、インプラントの寿命が縮むこともあります。
不適切な噛み合わせや埋入位置の調整ミスによってインプラントに過度な負荷がかかると、結果的にネジの緩みや骨吸収を引き起こし、寿命が縮みやすくなるのです。
だからこそ、インプラント治療は経験豊富な医師や専門医に対応してもらうことが推奨されるでしょう。
毎日の手入れ不足
毎日の手入れ不足によっても、インプラントの寿命は縮むことがあります。
天然歯と同様に、インプラントも毎日のセルフケアが欠かせません。
ブラッシングが不十分な場合、プラークが蓄積し、インプラント周囲炎のリスクが高まります。
もともと口内が健康で、周囲炎のリスクが低かった方でも、インプラントになってから炎症を引き起こしやすくなることがあるため、寿命を縮めないためにも丁寧なケアが必須です。
正しい歯磨きの方法や補助清掃用具の使用により、安定して使用できる環境を整えていくのが望ましいです。
インプラントの寿命を延ばす方法

インプラントは、使用者によって寿命を延ばすことが可能です。
ここでは、インプラントの寿命を延ばす方法について詳しく解説します。
お酒(飲酒)を控える
お酒は、インプラントの寿命に悪影響を与える要因の一つとされているため、治療を受ける場合は控えるようにしましょう。
アルコールの過剰摂取は、感染症リスクの上昇や免疫力の低下を引き起こす可能性があるだけでなく、歯周組織の血流障害や生活習慣病にもつながります。
結果的にインプラントの寿命にも影響する場合があるため、過度なアルコールは控えたいところです。
噛み合わせを調整する
インプラントの寿命を延ばすためには、噛み合わせを調整することが重要です。
不正な噛み合わせはインプラントに偏った力をかけ、上部構造や骨にダメージを与えることがあるため、定期的に咬合チェックを行い必要に応じた調整が必要となります。
他の歯並びに問題がある場合は、歯列矯正も視野に入れる必要があるでしょう。
食いしばり・歯ぎしりを抑える
食いしばりや歯ぎしりはインプラントに負担をかけやすいため、抑える必要があります。
無意識に食いしばりや歯ぎしりをしてしまっている方は、ナイトガードなどのマウスピースの装着により対処が可能です。
健康的な食生活を心がける
インプラントの寿命を延ばすためには、健康的な食生活を心がけることも重要です。
栄養バランスの取れた食事は、口腔内の健康維持に寄与します。
特に、カルシウム・ビタミンC・ビタミンDといった歯肉や骨の健康を維持する働きが期待できる栄養素は積極的に摂取するようにしましょう。
信頼できる歯科医院を選ぶ
インプラントを寿命まで使用し続けるには、信頼できる歯科医院を選ぶことが必須です。
実績が豊富な歯科医院での施術は、安定性と成功率に直結します。
また、症例数やCT診断の導入、学会認定医の在籍も基準に歯科医院を選ぶと良いでしょう。
タバコ(喫煙)を控える
タバコも、インプラントの寿命に悪影響を与える要因の一つとされているため、治療を受ける予定がある方は控えるようにしましょう。
継続的な喫煙は、血流障害を引き起こすだけでなく感染のリスクにもつながります。インプラントの寿命を延ばしたい場合は、喫煙自体を止めることが理想です。
定期的にメンテナンスする
定期的にメンテナンスするだけでも、インプラントの寿命は延ばすことが可能です。
3ヶ月から半年に1回といった具合に定期メンテナンスを行うことで、インプラント周囲炎や破損リスクを未然に防ぐ効果が期待できます。
歯医者に何度も通うのは億劫という気持ちもわかりますが、担当医の指示に従って適切にメンテナンスを受けましょう。
丁寧にブラッシングする
丁寧にブラッシングすることが、インプラントの寿命を延ばすことにつながります。
適切な歯ブラシはもちろん、インターデンタルブラシやフロスによって歯の隙間を清潔にすることで、口内に発生する炎症をある程度まで抑えることが可能です。
特に、歯茎との境目は炎症を引き起こしやすいため、丁寧にブラッシングすることを心がけましょう。
インプラントの寿命の判断基準

インプラントが寿命を迎えているかどうかは、インプラント体の脱落、上部構造の劣化、歯茎のトラブルから判断が可能です。
ここでは、インプラントの寿命の判断基準について詳しく解説します。
インプラント体の脱落
インプラント体が脱落した場合、寿命を迎えていると判断して良いです。
本来、インプラント体が勝手に脱落することは稀なため、脱落した場合は他に何らかの原因が考えられます。
特に原因がわからない場合は、迅速に担当医に相談しましょう。
上部構造の劣化
上部構造の劣化が認められる場合も、寿命を迎えていると判断できます。
上部構造は経年により摩耗し、咬合異常や審美的不具合が生じることも珍しくありません。
劣化の状態によっては、破損だけでなく変色などのトラブルが発生することもあるため、頃合いを見て交換が必要です。
歯茎のトラブル
何度も歯茎のトラブルが発生する場合、インプラントの寿命を疑いましょう。
インプラントに問題があると、歯茎の出血や退縮、発赤などを引き起こしやすくなり、最終的には周囲炎にまで発展する可能性があります。
不安な場合は、歯科用CTや歯周ポケット検査を受けると安心です。
インプラントの再手術が必要となるケース

インプラントに何らかの問題がある場合、再手術が必要です。
ここでは、インプラントの再手術が必要となるケースについて詳しく解説します。
インプラント周囲炎
インプラント周囲炎とは、インプラントの周囲に炎症が起こる疾患で、状況によっては再手術が必要となるケースがあります。
歯周病と同様にプラーク内の細菌が原因で、歯茎の痛みや膿、出血や腫れなどの症状を引き起こし、進行するとインプラントを支える骨が吸収され、最終的には動揺や脱落に至ります。
初期であればクリーニングや抗菌療法で治療可能ですが、重度の場合はインプラント体の除去と再埋入が必要となることもあるため、注意が必要です。
なお、再手術に関しては、定期メンテナンスと早期発見で回避可能です。
金属アレルギー
金属アレルギーの反応が出た場合、再手術が必要となる可能性があります。
本来、インプラントに使用されるチタンは生体親和性があり、金属アレルギーを起こしにくい素材なのですが、極めて稀にアレルギー反応を示す方がいます。
仮にアレルギー反応が出た場合、口腔内の違和感や全身性の発疹、粘膜のただれなどが見られるため、注意深く観察する必要があるでしょう。
アレルギーが疑われる場合は、皮膚科でパッチテストを行い、陽性であればインプラントの除去を行うことが必要です。
なお、現在ではジルコニア製のメタルフリーインプラントといったアレルギー対応の選択肢もあるため、再手術をする場合は材質にもこだわりたいところです。
神経障害
神経障害の症状が出た場合も、再手術が必要となる可能性があります。
主に、インプラントにおける神経障害は、下顎にインプラントを埋入する際に下歯槽神経に接近しすぎた場合に発生しやすいです。
症状としては下唇の痛みや感覚異常、痺れなどがあります。
そのため、手術前に精密な画像診断を行ってくれる歯科医院で治療を受けましょう。
精密な画像診断を行っている歯科医院であれば、患者に合わせた治療方針を組み立ててくれるため、より安心です。
まとめ
インプラントは、適切な手術と継続的なメンテナンスによって、10年以上の長期使用が可能な治療法です。
一方、噛み合わせの不良や細菌感染、生活習慣が原因で寿命が短くなることもあるため、術後のケアと定期的なメンテナンスが欠かせません。
なお、名駅歯科クリニック・矯正歯科では、インプラント治療においてCT診断による正確な埋入設計、経験豊富な歯科医師による施術、充実した保証制度をご用意しております。
術後も継続的なケア体制が整っており、定期的なメンテナンスプログラムを提供しています。
名古屋駅近くでインプラントをご検討の方は、ぜひ一度、名駅歯科クリニック・矯正歯科までお気軽にご相談いただけると幸いです。